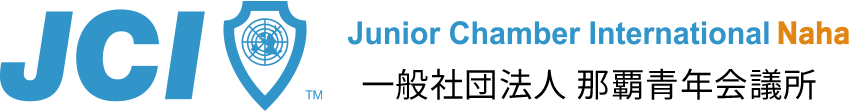一般社団法人 那覇青年会議所
第62代理事長 所信 大城 佑斗
2024年 基本理念
自由と規律
~報恩謝徳のまちづくり~
はじめに
未曾有の災禍も落ち着きをみせるなか、原点に立ち返り問いたい。
なぜ、那覇青年会議所(以下、JCI 那覇)は創立 60 年を超える今も存続し続けているのだろうか。国際的ネットワークを有する組織だからか。日本各地約 700 ある JCI 国内ネットワークがあるからか。私たちが住み暮らす地域へ貢献活動ができるからなのか。
そのどれもが私は違うと考える。
JCI 那覇が今日に至るまで継続し続けてきた理由はただ一つ。
魅力的な〝個〟がいたからに他ならない。
いつの時代にも常に魅力的な〝個〟が存在し、惹かれ合い調和する。そして次なる〝個〟が育ち次代に紡いでいく。まさに、JC 宣言文に記載のある通り、輝く個性が調和してきたからに他ならない。例えるならば、真っ火に燃える炭の側に、未だ燃えぬ炭を置くことで、少しずつ熱が伝播し、やがて真っ赤に燃える炭となる、そんな感覚に近いだろう。
それこそ JCI 那覇という組織の強さであり、青年会議所運動の根幹である「ひとづくり」と「まちづくり」に繋がってきたものなのだろう。そして、「ひとづくり」があってこその「まちづくり」であることを忘れてはならない。
心に火が灯る瞬間(魅力溢れる人財との出会い)
私は、起業を志し北海道、東京、沖縄で会社を設立し 2016 年に沖縄に移住した。
JCI 那覇に入会したのは 2017 年。青年期を沖縄で過ごしていない私は〝人との繋がり〟を切望していた。しかし、入会後に私が抱いた感情はその想いに反するものであり時間が合う時に参加する〝気まぐれ会員〟となった過去がある。
しかし、2020 年に転機が訪れた。
公益社団法人日本青年会議所 沖縄地区協議会(以下、沖縄地区協議会)への委員長としての出向だ。
ある方がこんなことを言っていた。
『JC には不思議な力がある』
私は、その〝JC の力〟というのを確かめることを決めた。
沖縄地区協議会に出向した 1 年は今では人生の宝になっている。
地域課題に対し本気で向き合った日々、議論沸騰に胸が躍り、事実確認のために関係各所への訪問、交渉、そのどれもが私には新鮮で刺激的な日々だった。そして、外務省、国際的民間団体、沖縄県知事、県内外で活躍する著名人、台湾デジタル担当大臣と交流を交わしていく中で〝JC〟の可能性を感じ、多くの〝力〟に触れることができた。
懐疑心が確信へと変わり〝気まぐれ会員〟の殻から抜け出したのもこの時だ。
単年度制という限られた時間の中で、私の心が赤く燃える炭になっていく感覚を体感した。素直に地域を良くしたい、水面に石を投げ込み起こる波紋のように、一つの小さなきっかけが次々と周囲に影響を及ぼしていく、そんな想いを共に持ち、地域課題に対し本気で向き合っていた会員は、まさに魅力的な〝個〟そのものだった。
私は、人の存在が自分を強くし、成長に繋がることを一人でも多くの会員に感じてもらいたい。その為に、JCI 那覇全会員の先頭に立ち、自らが率先し行動することで組織の魅力を内外へ発信する努力を惜しまないことを約束する。JCI 那覇の可能性を追求し、これまでとこれからを紡ぐ JCI 那覇のカタチを再構築する 1 年とし、今一度「ひとづくり」と「まちづくり」の大切さ、そして「ひとづくり」に重きを置き、規律を重んじながら自由な発想で地域に必要な活動を実行していくと誓う。
自由と規律(未来を駆ける先駆者たれ)
私たちが住み暮らす社会は規則やルールで溢れている。
これらが社会を支え、私たち一人ひとりの企業活動においても〝規律〟がそこにはある。
組織でいう〝規律〟は価値観だ。
確かな規律(価値観)のうえで自由な発想で活き活きと取り組むからこそ、強靭な意思と行動力が伴う〝個〟が集う組織は社会を変える力を持つ。
昨今、加速の時代といわれるなか「変化しないことがリスクになる時代」となった。
進化するテクノロジー同士が融合する「コンバージェンス(収束、統合)」により、テクノロジーは加速度的に進歩し 、私たちの住み暮らす社会に強烈な変化をもたらしてきた。
2009 年に爆発的に普及したスマートフォンなどが良い例であり、それらの登場は私たちの生活を一変させた。一方、急速な変化には歪みが生じるものだ。いつの時代もそれら変化を感じながらも地域とそこに住み暮らす人々のため、必要とする運動を JCI 那覇は展開してきたことだろう。積み重ねてきた実績は歴史であり語り継がれていくものである。
今一度、 JC の存在意義を再確認したい。
「日本の青年会議所は希望をもたらす変革の起点として輝く個性が調和する未来を描き社会の課題を解決することで持続可能な地域を創ることを誓う」
これまで幾度となく宣言してきた JC 宣言。
それこそが規律であり、理解し認知した活動こそが存続する意義である。
物事のはじまりを意味する「起点」は、青年会議所が「率先して行動する組織」であれという矜恃を表現し、私たちから社会変革を生み出していくという意志表示だ。そして、その運動によって生み出すものの本質は、誰もが、社会と自らの人生をより良くすることができると実感する「希望」であることを示しているのだ。
私たち JCI 那覇は、魅力溢れる〝個〟が集い、加速社会における未来を駆ける先駆者となるべく、強靭な意思と行動力を武器に地域社会に確かな気付きを与え続けることを誓う。
さぁ、自由な発想で行動しよう。
JCI 那覇の強みは間違いなく「ひとづくり」にこそある。
だからこそ掲げたい。
『自由と規律』こそが〝個〟としての心構えを育み、成長に繋がり、地域に必要不可欠な活ける財産(人財)となること。
未来への期待
観光産業、情報通信関連産業を県のリーディング産業に位置づけている沖縄県。
沖縄県といえば確かに観光業・宿泊業・飲食サービス業が県内産業の中心であり、製造業は少ないのが特徴的であるが、豊富な観光資源を背景に、開業率は全国 1 位。しかし、廃業率も高い。沖縄県内の起業・開業の業種別分類の上位は、「飲食店・宿泊業」「医療・福祉」「情報通信」「サービス業」となっており、比較的、参入障壁が低く、初期投資も低い業種が多いのも特徴であるが、開業時に苦労した点としては「自己資金の蓄積」「資金調達」「必要な知識・ノウハウの習得」などが挙げられ、それらの充実を図ることができれば起業成功確率が高くなるとも言える。
内閣府沖縄担当部局が「強い沖縄経済の実現」と掲げた令和 4 年度の資料がある。
そこには、県内総生産や就業者数が全国水準を上回り、改善傾向にあることを示している一方で、一人当たりの県民所得の低さ、コロナ禍による社会・経済情勢への影響による課題感もあげられていた。
沖縄県における自立的発展に向け、城外競争力の強化、民間主導による強い沖縄経済の実現を掲げ、「観光・リゾート」「農林産業・加工品」「IT 関連産業」「科学技術・産学連携」を重点 4 分野として選定している。
少し視点を変えてみると沖縄県では 7 万 8658 カ所の事業者が存在している。(個人経営が約 54%。法人が約 44%。その他が約 2%)従業者数も 10 人以下が約 80%を占め、中小企業・小規模事業者が99.9%の沖縄県においては資金面、人材面、情報の利活用におけるリテラシー面での課題も抱えていることがわかる。
事業/ビジネスの拡大において、新たなコンテンツの創出し続けることはビジネス全体の鮮度を保つ上で重要だが、そこには人財が必要不可欠だ。コンテンツの拡販には広報の力が必要で資金となる原資がいる。そして目まぐるしく移り変わる時代の流行を読み解く情報収集能力が必要だろう。果たして政府機関による取り組みは、これら課題を抱える小規模事業者たちには活用することができるのだろうか。
また、近年では、観光 2 次交通(2 次交通ツーリズム)を掲げ観光客の過度なレンタカー利用から公共交通の利用を促進し、観光客の利便性及び満足度の向上に取り組んでいる。
なぜ自動車保有率も高く、渋滞大国と言われる沖縄で ETC が普及していないのか。全国平均約 92%に対し、沖縄は約 65%と全国的にも低い普及率だ。ETC 専用レーンも一般と比較し1:9 の割合だ。観光立県を掲げ、多くの観光客が沖縄に来て楽しんでほしいと発信しながらも足元の状況はどうなのだろうか
人口に着目してみるとまた違う課題が浮き彫りとなる。
沖縄県の将来推計人口は、令和 12 年(2030 年)前後をピーク(147 万人)に減少に転じるとされているが、実際には 2022 年 10 月には、本土復帰した 1972 年以降で初めて人口が減少に転じた事実も忘れてはならない。出生率は全国 TOP である一方で、生涯未婚率(50歳時未婚率)は男女ともに全国平均を上回り全国 7 位と深刻な状況だ。少子化の要因の一つである未婚化・晩婚化により経済面では、労働力の減少→生産性の低下→経済規模の縮小が、社会面では、伝統文化の衰退→病院や公共施設の減少→地域活力の低下、と沖縄県経済に与える影響は深刻なものであるだろう。
私たち JC は、これら目の前にある山積みになった課題に対してどのようなことができるだろうか。子の世代には改善しているのだろうか。青年経済人が集う JC であれば、目を背けず、個性溢れる様々なアイディアを具現化し挑戦することができるのではないか。
それこそがリーダーとしての学びと機会の提供であり、個の成長に直結する JC たる運動であると信じている。
リーダーシップ(心育む人財育成)
2022 世界会議香港大会の総会で、JCI が「Leadership Development Opportunities(リーダーシップの開発と成長の機会)」をいかに重視しているかを正確に示すため、JCI Missionが再定義された。変化する世界に対応するリーダーを育成する組織であるということが明確に示されたのだ。
リーダーとは、指導者や統率者、先導者という意味を持ち、チームの目標達成や課題解決に向けてメンバーを束ねていく人を指す言葉だ。
リーダーシップとは指導力、統率力などと表現され、組織の中で目標を定め、組織を維持しながら成果を出す能力である。
JC という組織は、しばしば学舎と表現される。何を学び、何を得るのか。
それは、「ひとづくり」という言葉に全て集約されているのだろう。市民や行政の共感を得ながら、地域の特性を活かしたまちづくり運動を展開する上で、確かにリーダーシップは必要だろう。ここで私が考える〝リーダー〟について所信に示したい。
【リーダーの役割とは何か】
◆代表者であり、指揮者である
各会議や委員会などの責任者として出席し、組織間、他機関との連携および調整し、円滑な運営をはかる。そして、メンバーの確保と業務振り分け、士気の向上をはかる。例えるとオーケストラの指揮者である。
◆情報収集と伝達により時代の変化を伝えるスポークスマンである
組織全体の主な動きや他部門、各会議、各委員会などから情報を集め、組織としての目的・目標・動きを把握・伝達し、情報の共有化と協調関係の強化につとめる。
◆改革者であり、トラブル処理者である
事業の質向上と組織全体の質向上に向けて改善を行い、会員間トラブルなどに適切に対応して改善を行う。また、会員の仕事・家庭・健康状態にも気配りをしなければならない。
リーダーシップは生まれつきの才能ではなく、環境やトレーニングによって後天的に身につくものであり、経験の積み重ねによる実績により備わるものだ。そして、組織の状況により変化し、才と徳を磨き、人を心服させる能力を持つことで権威も備わるものであると考える。私は、これらリーダーとして学び得る機会の提供をする 1 年とすることを誓いたい。
数と継続に勝る力なし(動機に価値を)
JC は不連続の連続だ。単年度制であるが故に 1 年ごとに組織体制は変わる。
毎年変わりながらも 60 年を超える現在も存続している。
私は、事業を通して会員にビジネス(会員個々のビジネス発展)×拡大(自らの意思で入会を希望)×交流(会員同士の信頼関係の構築)の機会を提供したい。
昨今、JCI 那覇は、入会年次 3 年未満が半数を占めている。
多くは「〇〇に誘われた」という理由だ。
きっかけは人それぞれだが、魅力に触れ体感しなければ退会者に変わる。
〝JC しかない時代から JC もある時代〟へと変化していると言われるなか、会員一人一人に他団体・有識者との交流機会をつくり、事業への取り組み方を目の前で感じてほしい。
JCI ネットワークは年々拡大していることを忘れてはならない。
2020 年に JCI™ (Junior Chamber International)は BNI® (Business Network International)と世界各地の地域経済と世界経済を後押しするグローバルなビジネスリーダーを支援するために協力するパートナーシップを締結した。
2 つの組織が、グローバルな規模でのプラットフォームを活用することにより、ネットワーキングをより強固なものとし、周囲に影響を与えることのできるリーダーを育むことを継続することで、地域や世界経済をより良いものにしていくことを目指した連携だ。JCI 那覇においても異なるコミュニティが互いの強みを活かして協力し社会に価値を還元するロールモデルとなるよう連携体制を構築していきたい。
〜 One Impact can change the World 〜
人の影響力は世界を変えることだってできる。気づきによる納得感ひとつで、組織の活性化は進み、強力な力となる。数と継続に勝る力なし。
一人一人の強靭な意思と行動力が伴う〝個〟が集う組織は社会を変える力を持つ。
一人でも多くの方と想いを共有し、地域に対する運動に取り組んでいきたい。
JCI 那覇が誇る国際児童交流と友好の輪
JCI 那覇は、国家青年会議所として活動した歴史のある団体だからこそ国際連携には力を入れていきたい。現在、JCI 台北四海、JCI 香港北區、JCI マンダリンと姉妹締結をしているが、2022 年には広島県の JCI 呉と友好締結を結んだ。
広島といえば、1945年8月6日8時15分に広島市に投下された原子爆弾の悲惨さを物語る原爆ドームがあり、広島平和記念碑とも呼ばれている。その中で、呉市は、戦艦大和でも有名な軍港として発展してきた歴史がある。呉は明治時代、海軍の鎮守府が置かれ軍港として栄えた。当時、旧海軍条例によって日本近海の海域は五つの海軍区に分割され、海軍区ごとに鎮守府が設けられ統治が行われていた。鎮守府が設けられた理由は、瀬戸内海の島々に守られた内海に面し、防御の点で有利であったかとされている。同時に海軍兵学校や工場が設けられ軍備品や艦艇の修理などを行い製造業としての発展を遂げた地でもある。昨今のロシア、ウクライナの戦争により、日本/沖縄に住む私たちにとって対岸の火事
ではない。
世界的なパンデミックも収束に近づき、渡航制限が緩和される中、JCI呉も参加のもと、JCI台北四海、JCI香港北區、JCIマンダリンとの国際児童交流を再活性化したい。
国際児童交流、その目的はなにか。
言語や生活・習慣等の相違を越えた心と心のふれあいをもたらし、自己を確立し、他者を受容し共生しながら、発信し行動できる力を育成することに尽きる。
国際化した社会において、地球的視野に立ち、主体的に行動するための意識情勢において、JCI那覇の有する姉妹JC・友好JCとの繋がりは宝である。
AI(人工知能)の発展で英語学習が無意味なることなどない。
国際社会においては「対話」する能力は貴重な財産だ。沖縄がアジアの中心としての存在価値が高まっているいま、将来の地域を担う国際感覚豊かな青少年の育成に力を注ぐと共に、私たちが住み暮らす〝この場所〟が如何に素敵な地であるのか、体感し、これからの活動に活きる〝未来への心〟を繋げたい。
結びに
どの組織にも、個人にも危機は訪れる。
失敗とは外的要因だけでなく、自分の心の状態にあることも理解しておかねばならない。
正しい事だけして生きる事は出来ない、問題だらけなのが人生とわきまえ、他人を理解することなどできず、努力しても解決できないこともあるが、人生は最後の一瞬までわからないものであるから、人生は面白いのだ。
まさに JC を通して感じ得ることができることばかりだ。
それこそが JC が学び舎と称される理由なのだと私は思う。
基本理念『自由と規律〜報恩謝徳のまちづくり〜』のもと、自由を尊重し、規律を重んじ、〝個〟としての行動規律、組織ガバナンスの範囲の中で、〝個〟の柔軟なアイディアと、輝く個性が調和する未来を描くため、未来を担う人財育成、そして、これまでとこれからを繋ぐ 1 年とすることを誓う。